(New) 久しぶりに大学、学部の紹介やポリシー以外に文を依頼されました。霊長類学と獣医学の特徴と重要性を高校生レベルでもわかるように紹介してくださいとのことでした。優しく書くつもりでしたが、なかなか平易に書く癖がついていないので、硬い文章になってしまいました。学生さんが作ってくれる「教えて、よしかわ先生」のように書ければよかったのですが・・・・と反省しています。

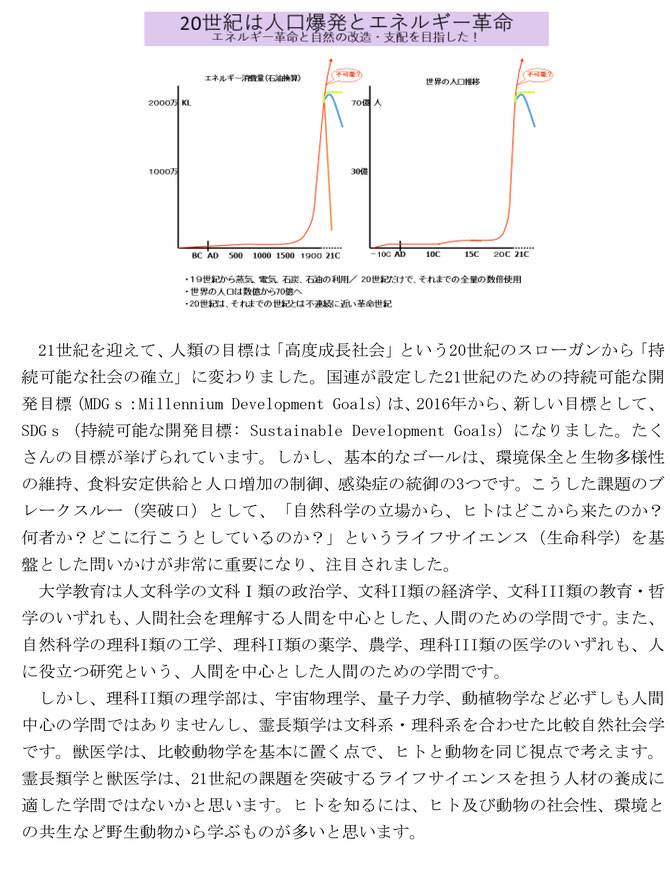

Philosophy of the New Faculty
The Sun and the Earth was born about 4.6 billion years ago. The first life emerged about 3.7 to 4 billion years ago as anaerobic autotrophic bacteria group. About half of the life history of 4 billion years on the Earth is the world of bacteria. Eukaryotic organism appeared about 2 billion years ago, and protozoa and algae were the highest creatures during about 1 billion years. Thereafter, multi-cellular organism group appeared about 1 billion years ago, and higher multi-cellular organisms appeared after the pre-Cambrian era about 500 to 600 million years ago. They evolved vertebrates eventually as fish, amphibians, reptiles, birds, and mammals.
This is the Earth's life history, but now the Earth has not changed the situation. Animals are not able to create a nutrition by themselves. Sugar and oxygen to become a source of energy for animal, are produced by the plant. Energy from the Sun is needed to plant photosynthesis, and carbon dioxide is discharged from the animal's breath. Circulation between plants and animals has created a sustainable situation. However, this is the visible energy circulation.
The nitrogen occupying 80 percent in the air is metabolized by nitrogen-fixing bacteria in soil such as rhizobia, and it will be used in the nutrition of the plant. The nitrogen will be returned from the soil or water to the air by the denitrifying bacteria. The same is true for phosphorus. Oxygen is also created by various algae and cyanobacteria, as well as plants. Algae and bacteria become the food for plankton and protozoa, and then plankton and small fish are eaten by larger fish. The fishes will be for human consumption as fisheries resources. Livestock and poultry also produce meat, eggs and milk, and they will be in service for human consumption. Such as food residue and livestock manure are the nutrient source for plants and soil bacteria as compost. Using the fermentation bacteria in the biomass will be used in methane and ethanol production. In this way, the atmosphere, water and soil are built, and are maintained on the foundation of the invisible bacteria, archaea, fungi and protists. Even now, the activity is continuing by bacteria (intestinal bacteria with a history of 4 billion years), and protists (environmental protists with a history of 2 billion years). Animals, plants and humans are able to keep alive on top of their activities.
However, environmental pollution goes rapidly by recent human activities, and it is approaching the self-cleaning and regeneration capacity limit. The Earth is only one star which has the life form in the neighboring space, and mankind has a responsibility for continuous protection of this star. The Earth is the common living home for all species and the human being. Over the excessive burden on the next generation, before passing the irreparable baton, what we must do? We need to know the secret of the playback mechanism and the resources circulation, which is conducted on this planet by both microorganisms and higher organisms. In addition, we need to find both crisis management and biological-measures, which enable the coexistence and harmony. The new faculty is standing in this perspective, we will conducted research and education to enable the Earth sustainable activities.
最近、新しい分野の教育・研究について思っていることです。感染症、共生と寄生、食料の安全保障、病原体の科学、危機管理学などを教えている間に、少しづつ気になっていたことです。
太陽と地球は約46億年前に誕生しました。最初の生命は、嫌気性独立栄養細菌群として約37億〜40億年前に現れました。地球上の40億年の生命史の約半分は、細菌の世界です。真核生物は約20億年前に登場し、原生動物や藻類は、約10億年の間は最高の生き物でした。その後、多細胞生物群は、約10億年前に出現し、高等多細胞生物は、約5億〜6億万年前のプレカンブリア時代の後に現れました。彼らは最終的に魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類などの脊椎動物に進化しました。
これは地球の生命の歴史ですが、今も地球の状況は変わっていません。動物は自分で栄養を作成することができません。動物のエネルギー源になる糖及び酸素は、植物によって産生されます。太陽からのエネルギーは植物の光合成に必要とされ、二酸化炭素は、動物の呼吸から排出されます。植物と動物の間の循環は、持続可能な状況を作り出しています。しかし、これは、可視エネルギーの循環です。
空気中の80%を占める窒素は、根粒菌のような土壌中の窒素固定細菌によって代謝され、そしてそれは植物の栄養に使用されます。窒素は脱窒菌により大気に土壌や水から返されます。同じことが、リンについても言えます。酸素はまた、様々な藻類やシアノバクテリアだけでなく、植物によっても作成されます。藻類や細菌は、プランクトンおよび原生動物のための食物となり、その後、プランクトンや小魚は、より大きな魚に食べられます。魚は漁業資源として人間に消費されます。家畜や家禽はまた、肉、卵、牛乳を生産し、それらは人間の消費のためのサービスになります。こうした食物残渣や家畜糞尿は、堆肥として植物と土壌細菌のための栄養源になります。バイオマスでは発酵菌を使用することにより、メタン、エタノール生産に使用されます。このようにして、大気、水、土壌が構築されており、目に見えない細菌、古細菌、真菌、および原生生物の基盤の上に維持されています。今でも、その活動は細菌(40億年の歴史を持つ腸内細菌)、および原生生物(20億年の歴史を持つ環境原生生物)により継続しています。動物、植物と人間は、その活動の上に生き続けることができるのです。
しかし、環境汚染は、近年の人間活動によって急速に進み、それは、自己浄化および再生能力の限界に近づいています。地球は、隣接空間で生命体を持っている唯一の星であり、人類がこの星の継続的な保護のための責任を負っています。地球はすべての種と人間のための共用の住み家です。次世代に過大な負担をかけて、取り返しのつかないバトンを渡す前に、我々は何をしなければならないのでしょうか?私たちは、微生物や高等生物の両方により、この地球上で行われている再生機構と資源循環の秘密を知る必要があります。加えて、我々は危機管理と共存と調和を可能にする生物学的対策の両方を見つける必要があります。新しい学部では、このような観点に立って、私たちは、地球の持続可能な活動を可能にするために、研究と教育を実施したいと思います。
レギュラトリーサイエンス(科学と政治)について、食品安全委員会プリオン専門調査会の時の経験をもとに、まとめたものです。やはり、時間がたたないと見えてこないものがあります。貴重な経験であったと思い、記録に残そうと考えました。
科学と社会‐BSE問題についての科学者の役割‐
千葉科学大学副学長・危機管理学部教授 吉川泰弘
はじめに
「福島原発災害後の科学と社会の在り方」という、この本の中で、ここで取り上げる事例は、他と違って直接的に原発事故と関連したものではない。著者がこれまでに体験してきた、食品安全委員会のプリオン専門調査会で行ったリスク評価の事例が、社会と科学の関係、政治と科学の問題に適合していること、原発事故後の科学者と社会の問題に共通している点があることのためである。
最近、レギュラトリーサイエンスという言葉が使われるようになった。科学と行政の橋渡しをすることを目的とした科学ということである。従来、政策の立案や政治的な決断、規制や基準の策定は、政治的な判断に基づいてなされてきた。しかし、近年、政治的な決定を科学的なリスク評価等に基づいて行おうという考え方(science based decision making)が国際的に受け入れられるようになってきた。国益や主義、思想などに基づく判断では、2国間あるいは多国間の調整が取れないため、中立的、科学的な分析を根拠に置こうというものである。
自然科学は中世の宗教から独立する目的で、中立性、客観性、再現性、普遍性などの要素をもとに、価値観や思想、主義という人文社会科学的なものを捨てることにより、独自に発展し、市民の信頼を得てきた。しかし、このレギュラトリーサイエンスという新しい科学は、再び、社会と科学、政治と科学を結び付ける方向に舵を切った。また、自然科学事態も、ビックサイエンスとして、社会全体に不可逆的な影響を与えるまでに肥大化してしまった。こうした状況の中で、科学と社会、科学と政治のあるべき関係が問われている。
1、BSE問題以前の個人的経験
1)基礎科学と社会の関係
大学で学んだ生命科学研究は、実験科学に基づくものである。そのプロセスは、「どのような実験仮説を立て、どのような材料と方法を用いて自分の仮説を証明するか?から始まり、実験の結果を考察し、そのうえで次の仮説を立てて研究を進めていく」というものである。この時のキーポイントは、立てた仮説がどのくらい本質的なものであるか?仮説には優れた独自性があるか?再現性、客観性は保証されているか?といったものである。国際誌に受理され評価されれば、一応のゴールで、その成果は、きっといつかどこかで社会に役立つだろうという認識であった。研究成果は専門家のコミュニティーで共有されれば十分で、直接的に社会に関係することは、ほとんどなかった。
2)自然科学の別の側面
1990年、大学の研究所から、小さいながら国の研究機関のセンター長として赴任した。国立試験研究機関には大学と違い、別のニーズと責務というものがあることを理解した。国家予算で賄われている省庁の国立試験研究機関の研究には、独自のミッションがあり、そこで得られる研究成果は、喫緊の社会的問題の解決につながることが重要なのである。大学での研究のように、問題の本質を解くというよりは、政治や行政が問題を解決するための基礎的な科学的データを提供する、あるいは法律や規制の根拠となる科学的なデータを作成するといった類のものである。それでも、本質的な部分は実験科学的な要素が多かった。
3)政治と科学
1999年、百年ぶりに改正された感染症法に人獣共通感染症が組み込まれた。約百年間、伝染病予防法は人から人への伝染病の統御を目的にしており、家畜伝染病予防法は家畜から家畜への伝染病の蔓延防止を目的としていた。動物から人に伝播する感染症(動物由来感染症、人獣共通感染症)は、それまで医学でも、獣医学でもほとんど取り上げられなかった。感染症法を作るにあたって、獣医から2名(他の1名は恩師の山内一也先生)の専門家として招聘され、責任を取ることとなった。人獣共通感染症の統御に必要な規制を順次法制化するにあたって、初めてリスク評価という基礎科学のアプローチとは異なる科学的方法論を学んだ。それまで政治的配慮でなされていた立法を、できるだけ科学的評価に根拠を置いた規制にしようという国際的な動きに対応したものであった。
2、BSEの経緯
1)牛海綿状脳症(BSE:Bovine Spongiform Encephalopathy)
牛海綿状脳症(BSE)は1986年に英国で発見され、1988年にBSEという名前で国際機関(国際獣疫事務局:OIE)に報告された。平均潜伏期が約5年という非常に長い、致死性の進行性中枢神経疾患である。英国では1992~93年が摘発のピークで、年間約3万頭以上の発症牛が見つかっている。公式発表では、18万頭を越える感染牛が出たとされている。疫学者により、比較的に早い段階で原因が肉骨粉(獣脂かすを含む)であることがつきとめられ、その後の対策も適切であったために、英国国内では流行は終息する傾向が見られた。しかし、余った肉骨粉が欧州を中心に国外に輸出された結果、汚染は欧州に広がった。欧州の汚染ピークは1995~96年であり、飼料規制により陽性牛の摘発は2002~03年をピークに欧州の流行も終息傾向となった。
1990年欧州が英国から肉骨粉の輸入を禁止した後、英国の肉骨粉はアジア、北南米などに輸出先が変更された。また欧州の汚染された肉骨粉も、自国での使用を禁止した後、アジア、北南米などに輸出された。そのため、BSE汚染は1990年代から2000年代にかけて世界中に広がった。世界では、英国を含め25カ国以上で総数約19万頭の感染牛が発見される結果となった。初発から約30年を経過し、現在では世界で年間数頭のBSE陽性牛が摘発される状況となっている。
2)変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD: variant Creutzfeldt Jacob Disease)
BSEは異常なプリオン蛋白が中枢神経系に蓄積し、海綿状の病変を惹起する疾病である。同様の疾病としては、欧州で200年以上にわたって羊のスクレイピーが知られており、人では全世界でクロイツフェルト・ヤコブ病が、パプアニューギニアでクールーが、特定の家系でゲルストマン・ストロイスヒャー・シャインカー病と家族性致死性不眠症などが知られている。
英国では1994年頃から、従来のクロイツェルト・ヤコブ病(CJD)とは臨床症状は異なるが、病変が類似する若年性の海綿状脳症患者が現れるようになった。異常プリオン蛋白の分子性状(糖鎖の付加パターン)や近交系マウスでの病変分布はBSEプリオンと類似していた。当初、BSEは羊のスクレイピーに由来すると考えられていたために、人への感染は起こらないと思われていた。しかし、1996年になって英国政府は、この新しいタイプのクロイツェルト・ヤコブ病(vCJD) は、BSEが原因である可能性を示唆した。このことは世界的なパニックを引き起こした。治療法のない致死性神経疾患が牛から人に伝播する可能性が示唆されたのである。
2013年7月までで、vCJD患者数は世界全体で228人(うち英国177人(輸血による感染例3人を含む)、フランス27人、スペイン5人など)である。英国では1990年に特定牛臓器(SBO;specified bovine offal,特定危険部位SRMに相当)の人への食用を禁止した。英国海綿状脳症諮問委員会(SEAC;Spongiform Encephalopathy Advisory Committee)の報告では「あの段階(1989年)において、もう少し強い規制をかけることを提言すべきだったかもしれないが、そのようなことをすれば、欧州の畜産業界に多大な打撃を与えることになると考えて、やめた」(リチャード・サウスウッド)と述べられている。
3、BSEの侵入と安全神話の崩壊
1)BSEの侵入と初期対応
英国におけるBSEのアウトブレイク(1992、93年)、および人のvCJDがBSE由来である可能性の示唆(1996年)は、研究者の不安を引き起こした。国際的な物流の拡大、流通量や頻度を考えれば、わが国へのBSEの侵入と国内での暴露・増幅の可能性は否定できなかった。欧州の科学運営委員会(SSC; Scientific Steering Committee、欧州食品安全機関EFSA;European Food Safety Authorityの前身 )は、独自の分析で、日本がBSEに汚染している可能性を示唆した。しかし、農水省はその可能性を否定してきた。国内にBSE牛が存在しないことを明らかにするための調査中に、2001年9月、BSE初発例が見つかった。初発例の診断を巡る混乱、陽性牛の対応への不備(焼却したはずの陽性牛が肉骨粉となって関西に運ばれていた)など、予測ミス、危機管理・初期対応の混乱が消費者に行政への不信を抱かせた。
2)安全神話の崩壊と不安の増幅
農水省は、長い間、日本の牛肉は安全だと消費者に説明してきたため、BSE問題発生後、消費者はパニックに陥った。EFSA(欧州食品安全機関)は以前から日本のBSEリスクについて評価し、警鐘を鳴らしていたのだが、農水省はそれに反論していた。そして農水省の安全宣言の1ヵ月後に1頭目の感染牛が出て、予測ミスだったことが明らかになった。しかも、感染牛は千葉県で偶然発見され、焼却処分したと主張したが、実際には肉骨粉として四国まで流通していたことが分かり、危機管理の不手際、対応の混乱とあいまって、行政への不信が頂点に達した。
消費者は、牛に肉骨粉を食べさせることは生物学上ありえない(共食い)という拒絶感や飼料添加剤などへの不安から、生産者への不信感を高めた。さらに、国産牛の回収にあたって、輸入・加工業者が虚偽申請したことへの不信感、また虚偽表示している流通・小売業者への不信感も高まり、モラルの崩壊が明らかになった。それに加えてメディアが毎日、BSEを発症した牛とvCJDの患者の映像を流して、明日の日本がこうなるかのような報道をした。最後に、専門家が出てきて科学というのは万能ではない。特にBSEはわからない問題ばかりで、科学の限界があること、ゼロリスクという確実な安全性は現実にはないことを指摘した。こうして、消費者は不安のどん底に叩き落とされることになった。わが国は従来、安全性を行政が保証し、国民は無批判にそれを受け入れる方式で、両者が折り合いをつけ、安全神話の安心感を共有する方式でやってきた。安全神話の上に立ってシステムの検証を行うこともしない。したがって、一度安全神話が崩れると、多かれ少なかれパニックを起こした後、システムの見直しをすることになる。
4、食品安全委員会(FSC:Food Safety Commission)
1)食品安全基本法
BSEの問題を受け、「食品安全基本法(2003年)」が制定された。
その第一条には、科学技術の発展、国際化の進展、国民の食生活を取り巻く環境の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、国・地方公共団体・食品関連事業者の責務、消費者の役割を明らかにし、施策の策定に係る基本的な方針を定め、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とする。
第三条には食品の安全性の確保は、必要な措置が国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に講じられることにより、行われなければならない。
第五条には、食品の安全性の確保は、必要な措置が食品の安全性の確保に関する国際的動向及び国民の意見(パブリックオコメント)に十分配慮しつつ科学的知見(リスク評価)に基づいて講じられることにより、食品を摂取することによる国民の健康への悪影響が未然に防止(予防原則)されるようにすることを旨として、行われなければならない。
第十一条には 食品の安全性の確保に関する施策の策定(リスク管理)に当たっては、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある生物学的、化学的、物理的な要因又は状態であって、食品に含まれ、又は食品が置かれるおそれがあるものが当該食品を摂取することにより人の健康に及ぼす影響についての評価(リスク評価)が施策ごとに行われなければならない、と書かれている。
産業振興と生産者重視できた施策、戦後、食の安全よりも食の安定供給を目指した施策をそのまま延長してきた行政に対して、根本的に考え方を転換させるものであった。
*( )は著者が挿入した。
2)食品安全委員会とプリオン専門調査会
BSE発生(2001年)後に、食品安全基本法とそれに基づく食品安全委員会が設置された(2003年)。準備委員会ではBSE問題の本質は、リスク評価とリスク管理と言う二つの要素がありながら、行政が評価と同時に管理するという役割も担っていたことにあったと総括した。このことを反省し、評価するものを管理するものと分断したほうがいいということで、各省庁の上に立つ内閣府に独立して、科学的・中立的立場でリスク評価を行う食品安全委員会を置くことになった。そこにプリオン研究の専門家等が集められ、BSEの問題について自分たちで分析し、世の中にはいろいろな意見はあるが、科学的に考えればBSEの危害、リスクがどの程度のものなのか?あるいは外国から来る牛肉、肉製品の危険性がどの程度のものなのか?といったことを評価する役目を負った。プリオン専門調査会はプリオン研究の専門家、公衆衛生、疫学、感染症の専門家など12名で構成され、独自の分析に基づいてリスク評価を行った。そして行政はリスク評価の結果に基づき、自ら決定した施策についてのリスクコミュニケーションを図るということになった。
3)食品安全委員会の構造と機能
BSE発生後に導入されたシステムがリスク分析手法であり、リスクの評価と管理を分離するため、内閣府に食品安全委員会が置かれた。食品安全委員会は、食品安全委員(7人、医・薬・獣医・報道関係者など)、事務局(農水省、厚労省からの出向者)及び、リスク評価の専門調査会(企画専門調査会を含む、約200人の専門家)からなっている。ゼロからスタートしたため、事務局は農水省、厚労省という管理機関からの出向者を充てることとなった。2~3年間、食品安全委員会で務めた後に、本省に戻っていくシステムが12年たった現在も行われている。
リスク評価では、ゼロリスクの否定、科学的評価に基づく政策決定(科学と政治の新しい関係)といった、全く新しい試みで消費者の信頼を獲得する方策を模索することとなった。リスク評価の基本は、リスク分析法に基づく。リスク分析は、社会科学と自然科学の両面をもち、リスク評価、リスク管理、リスクコミュニケーションの3つの要素から構成されている。
リスク評価は、食品中の危害因子を摂取することで起こる健康危害の確率(頻度)とその影響(社会的インパクトを含めて)の度合いを科学的に評価することを目的としている。専門家としては疫学、毒性学、公衆衛生学者などの科学者が多い。同時に、事実の分析と必要に応じてリスクモデルの作成も行い、危害が予測されれば不確実であっても予防原則にもとづいて予防措置をとることを勧める。
リスク管理は、リスク評価の結果を受けて、費用対効果、施策の実現性、国民の意識などを考慮しリスク管理措置を決め、国民にとった施策について説明する責任を負う。感染症のリスクは時間軸上で変化するものである。動的なリスク変動に対して、静的な管理措置(法律対応)を取ることになる。リスク管理者は、リスクが増加・軽減したときにリスク管理措置の強化・緩和をどのようにするかが、リスクコミュニケーションを含め主要な課題となる。情報の公開、容認しうるリスク範囲などに関してコンセンサスを得るための議論が必要である。
リスクコミュニケーションは前の2つに比べ、まだ曖昧である。リスク評価、管理に関する情報の開示は基本的に国民に判るように伝えられるべきである。そのためには、特に管理者である行政に説明責任があり、リスクとベネフィット、コストとベネフィットの納得の行く説明が必要である。コミュニケーションの重要なもう1つの要素は相互伝達性である。リスク評価およびリスク管理に対する再評価(有効性の検証)は必須であり、メディアを含め、消費者の側に立ってこの役割を行う集団がリスクコミュニケーターである。わが国では評価と管理の組織は出来たが、まだ評価者としてコミュニケーションを担う母体が出来ていないようである。
4)食品安全委員会の所掌事務(食品安全基本法第二十三条)
一 第二十一条第二項(内閣総理大臣は、食品安全委員会及び消費者委員会の意見を聴いて、基本的事項の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。)により内閣総理大臣に意見を述べること。
二 自ら食品健康影響評価を行うこと。
三 食品健康影響評価の結果に基づき、食品の安全性の確保のため講ずべき施策について内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。
四 食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。
五 食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に意見を述べること。他に、必要な科学的調査及び研究を行うこと。関係者相互間の情報及び意見の交換を企画し、及び実施すること。
食品健康影響評価を行ったときは、遅滞なく、関係各大臣に対して、その食品健康影響評価の結果を通知しなければならない。
委員会は、通知を行ったとき、勧告をしたときは、遅滞なく、その通知に係る事項又はその勧告の内容を公表しなければならない。
関係各大臣は、第三号又は第四号の規定による勧告に基づき講じた施策について委員会に報告しなければならない。
委員会の所掌事務は上記のように書かれている。準備委員会が食品安全委員会に新しい組織としていかに期待したかは、この条文を読めばよくわかる。しかし、当時、食品安全委員がどこまで理解していたか不明である。また、この条文を読めば、食品安全委員会のリスク評価が単純に科学的評価結果を伝えるだけではないことが明らかである。リスク評価は、管理措置として社会に直結するために、容易に政治に巻き込まれ、政争の具に利用される危険が付きまとう。どのようにこうしたリスクを回避するのかは、全く検討されないままに食品安全委員会はスタートし、走ってきてしまった。
5、プリオン専門調査会のリスク評価と明らかになった課題
1)中間取りまとめ(2004年9月)
日本のBSE浸潤率がどのくらいか?BSE対策で行われた施策の効果はあるのか?日本でvCJD患者が出るリスクはあるか?といった社会の疑問に対し、科学的立場で分析した最初の試みである。プリオン専門調査会はBSEに関する科学的不確実性を念頭に置きながら、科学的に判っていること、不明なことを1つずつ明らかにし、これまでに得られた知見を整理した。また英国のデータを基にヒトへのBSE感染リスクを見積もり、日本のvCJDのリスク評価を試みた。これまでのリスク管理措置の実施状況を検証し、リスク低減効果を評価した。結果として、2001年10月の法規制後のリスクは無視できるレベルで、法規制前に食用に回ったBSE感染牛は5~35頭、vCJDの発生する可能性は0.1~0.9人であると結論した。
「中間とりまとめ」は多くのメッセージを伝えている。①BSEに関しては科学的に不確実性が多く現時点で全てが説明できるわけではないという科学の限界。②特定危険部位(SRM)に異常プリオン蛋白の99%以上が集中しているが、と畜場で常にSRM除去が完全に行われていると考えるのは現実的でないこと。SRM以外に異常プリオン蛋白が蓄積する組織がないかどうかは、現時点で判断できない等、SRM除去の限界を指摘した。③と畜場でのBSE全頭検査についても検出限界以下の感染牛が存在しうること。全頭検査の結果から21ヶ月齢以上の牛では現在の検査法で感染が検出される可能性はあるが、それ以下の若齢牛でのプリオンの蓄積量は非常に少なく、20ヶ月齢以下の牛では陽性牛が検出されなかったという検査の限界を示唆した。
全ての会議は公開で行われ、議事録も全て名前入りで公開された。評価報告書は全て委員が自分たちで書いた。科学的リスク評価において透明性と公開性という要素は極めて重要である。評価結果のみならず、評価のプロセスを公開することは、科学的リスク評価への信頼性を得るための必須な要素であると思う。全国を回って報告書に基づく公開討議をし、パブリックコメントをもとめた。これらは全て初めての試みであった。プリオンという科学者にとってもわかりにくい病原体の感染症であったために、公開討議というよりは説明をすることに終始してしまった。実際には、科学が万能であってほしい、専門家はなんでもわかるという市民の素朴な希望を打ち砕くものであった。リスク評価自体が不確実性を多く含んでおり、ゼロリスクを証明するものではなく、確率論的な危害発生の推定結果であるということを伝えることは非常に難しかった。科学評価がいつも正しいとは限らないが、しかし、科学的評価をもとに考えてもらうしかないということは伝えられたかもしれないと思っている。この問題は、行政からの諮問でなく、食品安全委員会が「自ら評価」した課題であった(食品安全基本法、二十三条、第二項)。
2)国内対策見直し(2005年5月)
「中間とりまとめ」以後、リスク管理機関から国内対策見直しの諮問を受け、食品安全委員会としてはBSE迅速検査法(ELISA法)で検出困難な月齢の牛(20ヵ月齢以下の牛)を検査対象からはずした時のリスクの変動を明らかにすることが求められた。英国の発症牛の年齢の分布をどう評価するか?英国の実験感染例の評価、感染価の考え方、日本のBSE検査データの評価、英国・EU諸国の飼料規制等の効果の評価、日本のと畜工程・飼料規制の安全性の検証、日本での飼料規制等のリスク回避効果などを分析した。具体的には生体牛、食肉のリスク評価項目を設定し、定性的評価と定量的評価の2つの方法を試した。
分析結果として、日本のBSE汚染リスク、飼料規制と食肉加工の安全対策の有効性を背景に考えると、評価時点(2005年5月)で20ヶ月齢以下の個体を検査しなくても、検査した場合とのリスクの差は非常に少ないという結果になった。若齢感染牛では異常プリオン蛋白の蓄積量が少なく、検出は難しいが、特定危険部位を除くなら安全性は確保できるというものであり、全頭検査の限界を明示することとなった。世界でも類例のない全頭検査の導入により感染牛を摘発し、ゼロリスクが得られることを示唆する、政治的プロパガンダ、新しい安全神話の否定であった。しかし、この評価は多くの問題を噴出させた。
このリスク評価は①リスク管理には全く反映されなかった。リスク管理機関は全頭検査を続ける方針を示したまま、リスク評価を求めるという矛盾を犯した。リスク評価に基づく管理措置をとるために諮問するのではなく、3年間延長という管理措置を決めた後に諮問したのであるから、食品安全委員会のリスク評価は3年後にすると回答すべきだったかもしれない。あるいは3年延長という管理措置は科学的には間違っているという回答でもよかったのかもしれない。②研究者も全頭検査の科学的意義と安心のための管理措置の違いを説明できなかった。リスク管理機関の明確な説明責任が果たされないまま、リスク評価と管理の乖離を容認してしまった。③もっとも、深刻な問題は、パブリックコメントであった。約7割の意見は、20か月齢以下の検査の廃止を拒否する意見であった。パブリックコメントはプリオン専門調査委員会に戻ってきた。食品安全基本法第五条の「必要な措置が食品の安全性の確保に関する国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて講じられることにより、食品を摂取することによる国民の健康への悪影響が未然に防止されるようにすることを旨として、行われなければならない。」が、専門調査会の問題となったのである。1年以上をかけて議論した専門家の結論が、市民の不安によって変わるはずはなく、リスク評価と消費者の安心感の乖離は解消する方法が見つからなかった。また、3年後の検査見直しの実行は、事実上困難な事態となった。科学的評価がリスク管理機関、消費者に理解されなかった事例となった。
今、振り返ってみると、専門調査会の科学的評価は分析結果を出した段階で終了し、パブリックコメントを受け取るのは親委員会である食品安全委員会であるべきであった。リスク評価とパブリックコメントの乖離を埋めるためリスク管理側と調整する、あるいは20ヵ月齢でなく、30ヵ月齢、全頭検査廃止であればどのようなリスクになるか、自ら評価のテーマとするといった工夫があっても良かったと思われる。諮問に答えるだけでなく、自ら評価を追加して、リスク評価の科学的意味を社会に知らせる方法もあったかもしれない。
諮問には、諮問通りに応えなければならないか?分析結果は一通りしかないのか?食品安全委員会としては、こうしたことを検討する機会がなかった。英国のリスク評価では、しばしば、評価結果が複数提示されることがある。例えば規制措置を緩和した場合、緩和措置がごく一部であればリスクはこの程度増加するが、費用はこの程度削減される。さらに緩和すればリスクは増加するが、費用はさらに削減される、全面解除すればリスクはかなり上がるが、費用は掛からない、といった具合である。ゼロリスクがないとすれば、どのレベルが、その時点で受け入れられるリスクになるのか、複数のモデルを提示して、パブリックオピニオンを求め、リスク管理措置を決めるという手順である。リスク評価は科学的なモデルを提示するという役割になり、最終的な管理措置を決めるのは政治や行政ということになる。ここで必要な要素が、双方向性のリスクコミュニケーションということである。
3)米国・カナダ産の牛肉等の評価(2005年12月‐専門調査会の分裂)
国内対策見直しの後、米国・カナダの輸出規制プログラム(EVプログラム;the USDA Export Verification Programs)で管理された牛肉・内臓を摂取する場合と、我が国の牛に由来する牛肉・内臓を摂取する場合のリスクの科学的同等性に関する諮問を受けた。プリオン専門調査会は審議の基本方針として、我が国のBSE対策の見直しに関する諮問の際に用いたリスク評価項目について米国・カナダと日本の相違を検討し、総合評価を行うこととした。
今回の諮問では、国外の牛肉等のリスク評価を行うという状況のため、食肉のリスクに関しては文書に書かれた原則が主体で、一部、リスク管理機関からの情報及び専門委員などからの補足説明をもとに評価せざるを得なかった。したがって、不明な側面が多くあることを考慮する必要があった。日本と米国・カナダのデータが質・量ともに異なること、EVプログラムの遵守という仮定を前提に評価しなければならなかったことから、科学的同等性を評価することは困難といわざるを得ないという結論となった。他方、日本で年間に処理される全月齢の牛に由来する食肉等とEVプログラムが遵守されると仮定した場合の米国・カナダの牛に由来する食肉等のリスクレベルについては、月齢判定による上限を超えない範囲(20ヵ月齢以下)では、そのリスクの差は非常に小さいと考えられる。もし、輸入解禁に踏み切ったとしても、遵守が十分でなく、人へのリスクを否定することができない場合は一旦輸入を停止することも必要となる。また、安全性を確保するには、SRM除去の確認と検証、充分なサーベイランスの継続、完全飼料規制の導入が必要であると結論した。
しかし、この結論は委員会の中でも紛糾し、統一的見解とは言えなかった。委員の半数近くは、これを機会にプリオン専門調査会の委員を辞任した。科学的でないという意見もあったし、専門家の中で意見が一致しない場合の対応をどうするか?考える余裕がなかった。今回の諮問に対する回答では科学的同等性は評価困難という結論になった。科学的予測に置く前提が大きすぎる場合、現実的なリスク評価が可能かどうかという問題を提起することにもなった。評価後の問題としては、リスク管理機関の安全性検証の不足と脊柱の混入が発見されたため輸入が再停止した。米国と日本の許認可システム等には違いがある。日本の管理システムはトップダウン方式だが、米国はボトムアップ方式をとっている。日本のシステムが無謬性を基本とするのに対し、米国は検証と修正を基本においている。BSEリスクの認識の違い、人為的ミスに対する扱いの違いは、輸入を再開する際に両国の管理機関が認識を共有し、国民に説明しておく必要があると思われた。また、メディアは日米関係のパワーゲームとしてこのリスク評価の過程を報道し続けた。愛国主義論や政争の具に使うバイアスにより、科学者はリスク評価という任務に疲れ果てたという思いが強い。
4)BSE非発生国からの牛肉等のリスク評価(座長としての最後の評価,2009年)
我が国は、これまでに評価を終えた米国・カナダ以外の国からも牛肉及び牛内臓を輸入している。これらの国については、現在までBSE感染牛の発生が報告されていない。しかし、欧州食品安全機関による地理的BSEリスク(GBR)評価でカテゴリーIII(BSE感染牛が存在する可能性は大きいが確認されていない、あるいは低いレベルで確認されている)とされた国やGBR評価を受けていない国も含まれている。リスク管理機関は、これらの国からの牛肉等の輸入に際し、健康な牛の牛肉等であることを記載した衛生証明書や特定危険部位の輸入自粛を輸入業者に求めている。しかし、輸出国におけるBSEの有病率や対策が不明な部分もあり、牛肉等の潜在的なリスクが必ずしも明確になっていない。このため、食品安全委員会では自らの判断により食品健康影響評価を行う案件として、我が国に輸入される牛肉及び牛内臓に係る食品健康影響評価を行うこととした。
この評価では、これまでモデルとした欧州食品安全機関の評価方法では限界があるとして、日本独自の評価方法を開発した(評価方法は英文の論文として受理された、(Alternative BSE risk assessment methodology of imported beef and beef offal to Japan. Y. Yoshikawa, et al., J. Vet. Med. Sci, 2012, 74,959-968)。データを送ってくれた国由来の牛肉等のリスクは、現時点の各国のリスク管理措置であれは無視できるという結果になった。
評価を進めている途中で、著者の人事が国会人事マターとなり、ねじれ国会の結果否定された。その時の民主党の主張は米国・カナダ産のリスク評価が科学的でなかったというものである。日本学術会議は政府に反論を出してくれた。各国にリスク評価の結果を通知しているプリオン専門調査会の座長が、その正当性を立法府で否定された限り、座長を続けることは相手国に対する侮辱であるとして、辞任を申し出た。食品安全委員会に慰留され、評価を全うした後、7年の任期満了でプリオン専門調査会を退いた。科学と政治の関係の難しさを身にしみて知った出来事である。
おわりに
BSEのリスク評価をもとに、自分の経験から、科学と社会、科学と政治の在り方を振り返ってみた。自然科学者は、もともとこの分野が不得手である。基本的にこの種の現象は複雑系の問題であり(非線形性)、単純化が不可能である。また、取った対応が次のモデルに影響し(介入性)、やり直しがきかない(一回性)。これらは、従来の実験科学と全く違う。通常の実験科学の研究者は、研究室の中にいて実験し、またその結果を見て実験を進めていくという形でやってきたわけであるが、リスク評価では実験と全く違う次元の対応が要求される。リスク評価の役割を担う科学者は、その役割と責任を負う覚悟が必要である。また、人文社会科学者と連携していく能力も必要である。
東日本大震災後と共に起きた福島第一原発事故を巡って、科学と政治の在り方が問われた。福島原発のリスクを検討した委員会、事故後に設置された原子力規制委員会、放射能汚染のリスク評価を巡る専門家の対応等は、これまで述べてきた食品安全委員会の経験した問題点と非常に類似している。今回、発足して10年以上を経過した食品安全委員会を、福島原発事故後の科学と社会が突き付けた問題の視点で見ることが出来たことに感謝している。Science (科学)とPolitics(政治)の新しい関係が、一体どういう対応になっていて、どういうレベルで問題が解決できるか?実は私自身、まだ答えが出ていない。もう一度、今回の提言「科学と社会のよりよい関係に向けて―福島原発災害後の信頼喪失を踏まえて―」を読み直している。
最近、「人の脳とサル類の脳の構造、機能的な違い」について、原稿を依頼されました。 筑波の霊長類センターで、サル類を用いたモデル疾患研究をしていた時や、21世紀COEで「言葉と脳」のプロジェクトをしていた時は、夢中でしたが、こうして少し離れてみると、また違った見方でものを考えるようになりました(2015年5月脱稿)。次世代の研究者に少しでも、刺激になればと思います。







 吉川泰弘の
ホームページへようこそ!
吉川泰弘の
ホームページへようこそ!








